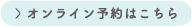本プログラムは4つの施設群からなる、地域社会に根ざした臨床実践的な内容のプログラムであり、「患者さんの価値と人権を尊重しつつ、科学的な知見に基づいた精神疾患の治療ができるようになること。医師としての基本的態度、心構え、学習法を身につけること。」を目的としています。
基幹施設であるむつみホスピタルは283床からなる民間の単科精神科病院であり、徳島県東部の精神医療の中核的な役割を果たしてきました。ここでは、主要な精神疾患の患者を担当し、指導医や他職種のスタッフによる指導を受けながら、専門医として必要な知識、精神療法、クロザピンを含めた薬物療法の基本を学びます。
また、精神科救急治療病棟、療養病棟、措置入院病床、認知症疾患医療センター、訪問看護ステーション、アルコールリハビリテーションプログラム、B型作業所、宿泊型自立訓練事業所、相談支援事業所を有しているため、急性期から慢性期、児童思春期から老年期までの幅広い年齢層・疾患領域の症例や精神科リハビリテーション、訪問診療、就労支援を経験できます。連携施設としては、八王子市の平川病院、高知市の土佐病院、東京大学医学部付属病院があります。民間の精神科病院である土佐病院、平川病院も精神科救急治療から慢性期に至るまで多彩な症例を経験できるため、むつみホスピタルでの約1年間で経験できなかった研修項目を補完できます。
また、東京大学医学部附属病院では、リエゾン診療やmECTの習熟のほか、専攻医を対象とするセミナーが開催されており、診断・治療だけでなく、精神療法や精神症候学、心理検査等、幅広い内容を学ぶことができます。専攻医は日本精神神経学会の精神科専門医制度専攻医研修マニュアル(以下研修マニュアル)をもとに研修を行います。
①臨床現場での学習
| (1) | 入院・外来などの治療場面において診療の経験を積み、自立して診療に当たることができるようにする。 |
|---|---|
| (2) | 自らの症例を提示して、カンファレンス等を通して病態と診断過程を理解し、治療計画作成の理論を学ぶ。 |
| (3) | 抄読会や勉強会を通して、またインターネットにより情報検索の方法を会得する。 |
以上の学習を効果的に行うために月間スケジュール・週間スケジュールなどを作り、設備などの充実を図ります。
②臨床現場を離れた学習
| 研修項目に示されている内容を日本精神神経学会やその関連学会等で作成している研修ガイドライン、e-learning、精神科専門医制度委員会が指定したDVD・ビデオなどを活用して、より広く、より深い知識や技能について研鑽します。患者に向き合うことによって、精神科医としての態度や技能を自ら学習する姿勢を養い、生涯に渡って学習する習慣を身につけます。 |
| 1年目: | 研修指導医と一緒に統合失調症、気分障害、器質性精神障害の患者等を受け持ち、良好な治療関係を築くための面接の仕方、診断と治療計画、 薬物療法及び精神療法の基本を学びます。とくに面接によって情報を抽出し診断に結びつけるとともに、良好な治療関係を構築し維持することを学びます。 |
|---|---|
| 2年目: | 研修指導医の指導を受けつつ、より自立的に面接の仕方を深め、診断と治療計画策定の能力を充実させ、薬物療法の技能を向上させます。専門的な精神療法として認知行動療法と精神行動的精神療法の基本的考え方と技能を学びます。 精神科救急に従事して対応の仕方を学びます。神経症性障害及び種々の依存症患者の診断・治療を経験する。また、リエゾン・コンサルテーション精神医学を経験します。 |
| 3年目: | 研修指導医から自立して診療できるようにします。診断と治療計画及び薬物療法の診療能力をさらに充実させるとともに、認知行動療法、精神行動的精神療法、森田療法・内観療法のいずれかについて、指導者の下で経験する。慢性統合失調症患者等を対象とした心理社会的療法、精神科リハビリテーション・地域精神医療等を学びます。児童・思春期精神障害、アルコールや薬物依存及びパーソナリティ障害の診断・治療を経験します。 ※実際の学習時期については各研修施設群において現実的に対応することとします。 |
| 1年目: | 院内カンファレンスで受け持った症例について発表し質問に答える。 |
|---|---|
| 2年目: | 院内カンファレンスで受け持った症例について発表し質問に答えるほか、他の医師の症例についても討論する。 |
| 3年目: | 院内カンファレンスでの発表、討論に加え、外部の研究会などで症例発表する。 |
1年目から、
| 1) | 自己研修とその態度 |
|---|---|
| 2) | 精神医療の基礎となる制度 |
| 3) | チーム医療 |
| 4) | 情報開示に耐える医療について生涯に渡って学習し、自己研鑽に努める姿勢を涵養します。2年目には、科学的思考、課題解決型学習、生涯学習、研究などの技能と態度を身につけ、3年目にはその成果を社会に向けて発信できます。 |
コアコンピテンシーとは、精神科専門医にとって極めて重要な核となる能力であり、次の1)~10)の項目が挙げられます。
| 1) | 患者や家族の苦痛を感じ取れる感性を錬磨し、苦痛を和らげるための努力を続ける姿勢。 |
|---|---|
| 2) | コミュニケーション能力を向上させて、チーム医療に積極的に参加し、必要に応じてリーダーシップをとれる姿勢。 |
| 3) | 情報開示に耐える適正な医療を行う姿勢 |
| 4) | 謙虚さと厳しさをもった自己研鑽の態度 |
| 5) | インフォーム・コンセントを実施できる。 |
| 6) | 後進の指導ができる。 |
| 7) | 科学的根拠となる情報(EBM)を収集し、それを臨床に適用できる。 |
| 8) | 科学的思考、課題解決型学習、生涯学習の姿勢を身につける。 |
| 9) | 症例呈示と討論ができる。 |
| 10) | 学術集会に積極的に参加する。 |
また、医師としての倫理性、社会性として、次の1)~12)の項目があげられる。
| 1) | 患者、家族のニーズを把握し、患者の人権に配慮した適切なインフォームドコンセントが行える。 |
|---|---|
| 2) | 病識のない患者に対して、人権を守る適切な紳士的、法律的対応ができる。 |
| 3) | 栓心疾患に対するスティグマを払拭すべく社会的啓発活動を行う。 |
| 4) | 多種職で構成されるチーム医療を実施し、チームの一員としてあるいはチームリーダーとして行動できる。 |
| 5) | 他科と連携を図り、他の医療従事者との適切な関係を構築できる。 |
| 6) | 医師としての債務を自律的に果たし信頼される。 |
| 7) | 診療記録の適切な記載ができる。 |
| 8) | 患者中心の医療を実践し、医の倫理・医療安全に貢献する。 |
| 9) | 臨床現場から学ぶ技能と態度を習得する。 |
| 10) | 学会活動・論文執筆を行い、医療の発展に寄与する。 |
| 11) | 後進の教育・指導を行う。 |
| 12) | 医療法規・制度を理解する。 |
1年目に研修基幹病院で研修を行い、1~3年目の間に研修連携施設をローテートするパターンと、1~2年目に研修連携施設をローテートした後、3年目に研修基幹施設で研修を行うパターンがあり、研修医の希望によりどちらかのパターンを選択できるものとします。いずれのパターンでも精神科専攻医研修マニュアルに従って研修を行います。
| ① | 医療法人社団 光生会平川病院 |
急性期治療病棟、精神科合併症病棟、認知症治療病棟、アルコール治療を中心に行う病棟をもっています。地域精神科身体合併症救急連携事業、拠点型認知症疾患医療センター事業も行っています。全身麻酔を伴った電気経連療法やクロザピンも処方で経験をつむことができます。外来部門では、認知症専門外来、発達障害専門外来を有しています。 |
|---|---|---|
| ② | 土佐病院 | 高知市中央圏の中核病院であり、高知大学精神科の学生実習協力病院でもあります。精神科救急に取り組んでいるほか、医療観察法に関する認定施設でもあり、精神科リハビリテーションに関する研修が充実しています。 |
| ③ | 東京大学医学部 付属病院 |
施設としての特徴:多種職によるチーム医療を実践しています。ECT,クロザピン処方など難治例の治療にも取り組み、身体合併症例の治療も積極的に対応しています。また、てんかんモニタリングユニットによるてんかんの鑑別診断、近赤外線スペクトロスコピーを中心とした短期検査入院、リエゾン診療、児童思春期精神医療、精神科リハビリテーションを研修します。 |
| ① | 外来診療、夜間当直、救急対応などを通して地域医療の実情と求められている医療 |
|---|---|
| ② | 精神保健の観点から疾病予防や地域精神医療が持つべき役割 |
| ③ | 関連する法律、制度について学習し、精神科専門研修等において関連法規する入院や通院医療の実際について学習する。 |
①形成的評価
当該施設研修での研修終了時に、専攻医は研修目標の達成度を評価する。
その後に研修指導医は専攻医を評価し、専攻医にフィードバックし、研修指導責任者に報告する。
また、研修指導責任者は、その結果を当該施設の研修委員会に報告し、審議の結果を研修プログラム管理委員会に報告する。基幹施設の研修指導責任者は、年度末に1年間のプログラムの進行状況ならびに研修目標の達成度について専攻医に確認し、次年度の研修計画を作成する。
なお、専攻医の研修実績および評価の記録には研修実績管理システムを用いる。
| 評価項目・基準と時期: | 研修プログラム統括責任者は最終研修年度の研修を終えた時点で研修期間中の研修項目達成度と経験症例数を評価し、それまでの形成的評価を参考として、専門的知識、専門的技能、医師としての備えるべき態度を習得しているかどうか、ならびに医師としての責任があるかどうかをプログラム管理委員会の審議を経て判定します。 |
|---|---|
| 評価の責任者: | 当該研修施設での最終的な研修評価については研修指導責任者が行います。また、研修施設群全体を総括しての評価を研修プログラム統括責任者が行います。 |
| 多職種評価: | 当該研修施設の研修指導責任者は専攻医の知識・技術・態度・コミュニケーション能力のそれぞれについて勘案して当該施設の研修指導責任者が専攻医にフィードバックを行い、当プログラム管理員会に報告します。総括的評価もその結果に基づいて、研修プログラム管理委員会が行います。 |
研修基幹施設の研修プログラム管理委員会において、知識、技能、態度それぞれについて評価を行い、総合的に修了を判定します。
研修プログラムの作成やプログラム施行上の問題点の検討や再評価を継続的に行います。
また各専攻医の統括的な管理(専攻医の採用や中断、研修計画や研修専攻の統括的な管理環境の整備など)や評価、専攻医および指導医に対して助言、修了の判定を行います。
| 1) | 勤務時間は週40時間を基本とし、時間外勤務は月に80時間を超えない。 |
|---|---|
| 2) | 適切な休日を保証する。 |
| 3) | 当直業務と時間外診療業務は区別し、それぞれに対応した適切な対価が支給される。 |
| 4) | 当直あるいはや夜間時間外診療施設の待遇等は区別し、適切なバックアップ体制を整える。 |
| 5) | 各研究施設の待遇は研修に支障がないように配慮する。 |
| 6) | 原則として専攻医の給与等については研修を行う施設で負担する。 |
研修プログラム統括責任者は、定期的に専攻医と面接を行い、研修プログラム及び研修指導医に対する評価を得ます。
専攻医による評価に対し、当該施設の研修委員会では改善・手直しをするが、研修施設群全体の問題の場合は研修プログラム管理委員会で検討し、対応します。
| 採用方法: | 基幹施設において面接等を行い、専攻医として受け入れるかどうかを審議し、認定します。 |
|---|---|
| 修了要件: | 精神科専門研修施設で、精神科専門研修指導医の下に、研修ガイドラインに則って3年以上の研修を行い、専攻医と研修指導医が評価する研修項目表による評価、多職種による評価、経験症例数を参考に、研修プログラム統括責任者により受験資格が認められたことをもって修了したものとします。 |
日本専門医療機構による「専門医制度新整備指針(第二版)」Ⅲ-1-④記載の特定の理由のために専門研修が困難な場合は、申請により、専門研修を中断することができます。 6ヶ月までの中断であれば、残りの基幹に必要な症例等を埋め合わせることで、研修期間の延長を要しません。また6ヶ月以上の中断の後、研修に復帰した場合でも、中断前の研修実績は、引き続き有効とされます。 他のプログラムへ移動しなければならない特別な事情が生じた場合は、精神科専門医制度委員会に申し出ることとします。精神科専門医制度で事情が承認された場合は、他のプログラムへの移動が出来るものとします。 また、移動前の研修実績は、引き続き有効とされます。
日本精神神経学会によるサイトビジットを受けることや調査に応じます。研修プログラム統括責任者、研修指導責任者、研修指導医の一部、専攻医が対応する。専門研修プログラムに合致しているか、専門研修プログラム申請書の内容に合致しているかについての審査を受けます。
| モデル1 | モデル2 | |
| 1年目 | むつみホスピタル | 東京大学医学部付属病院 平川病院 土佐病院 のうち、1又は2施設 ※研修期間は1施設時は1年、2施設時は6ヶ月ごと |
| 2年目 | 東京大学医学部付属病院 平川病院 土佐病院 のうち、1又は2施設 ※研修期間は1施設時は1年、2施設時は6ヶ月ごと |
東京大学医学部付属病院 平川病院 土佐病院 のうち、1又は2施設 ※研修期間は1施設時は1年、2施設時は6ヶ月ごと |
| 1年目 | 東京大学医学部付属病院 平川病院 土佐病院 のうち、1又は2施設 ※研修期間は1施設時は1年、2施設時は6ヶ月ごと |
むつみホスピタル |
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
| 8:00-8:15 | 病棟カンファレンス | 訪問カンファレンス | 外来カンファレンス | 病棟カンファレンス | 病棟カンファレンス |
| 8:15-8:45 | 病棟回診 | (同上) | (同上) | 病棟回診 | 病棟回診 |
| 8:45-9:15 | 診療業務連絡会 | 診療業務連絡会 | 診療業務連絡会 | 診療業務連絡会 | 診療業務連絡会 |
| 9:00-12:00 | 病棟業務 | 訪問診療 訪問看護 |
外来 | ARPなど | 病棟業務 |
| 13:00-16:00 | デイケア 社会復帰施設など |
作業所など | 医局会 CRAFTなど |
多職種カンファレンスなど | 専門外来 |
| 16:00-16:30 | クルズス | 抄読会 | 症例検討会 | ショートレクチャー | ショートレクチャー |
ARP:アルコールリハビリテーションプログラム
CRAFT:依存症家族支援プログラム
上級医と共に当直研修あり
| 4月 | オリエンテーション、初任者研修、日本統合失調症学会(任意)、地域向け祭り(むつみフェス) |
|---|---|
| 6月 | 日本リハビリテーション医学会(任意)、日本精神神経学会総会(任意) |
| 7月 | 日本うつ病学会(任意)、前年度研修実績報告書提出 |
| 9月 | 徳島精神科臨床懇話会・精翠会(任意) |
| 11月 | 日本児童青年精神医学会総会 |
| 2月 | 法人主催市民向け公開講座 |
| 3月 | 総括的評価、研修プログラム評価報告書作成 |
お電話でのご予約・お問い合わせは
088-631-0181